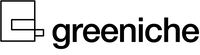北欧のフリーマーケット「ロッピス」に学ぶ、持続可能な暮らしの知恵
公開日: 2025年02月14日 (更新日: 2025年07月04日)
使い捨てるのではなく、受け継ぐ暮らしへ。
大量生産・大量消費の時代から、「長く大切に使う」暮らしへとシフトすることが求められています。そんななか、北欧で古くから親しまれているフリーマーケット「ロッピス(Loppis)」は、まさにサステナブルな暮らしを体現する場。
物を捨てるのではなく、新たな持ち主のもとへと受け継ぐ。その背景には「本当に良いものを選び、長く使う」という北欧ならではの価値観があります。
今回は、ロッピスの魅力を深掘りしながら、持続可能な暮らしを実践するヒントを探ってみましょう。
ロッピスとは? 単なるフリーマーケットではない北欧の知恵
ロッピスとは、スウェーデンをはじめ北欧諸国で広く行われているフリーマーケットのこと。春から夏にかけて、庭先やガレージで開かれることが多く、家族総出で不要になった家具や食器、衣類などを販売します。
しかし、ロッピスは単なる「中古品販売」の場ではありません。
そこには「物を最後まで使い切る」という北欧の暮らしの哲学が息づいています。スウェーデンやデンマークでは、新品を買うよりも「今あるものを活かす」ことに価値を置く文化が根付いており、ロッピスはその実践の場となっています。
たとえば、ヴィンテージのダイニングテーブルには、何世代にもわたる家族の食卓の記憶が刻まれ、使い込まれたレザーソファには、これまでの持ち主の暮らしの温もりが宿っています。
新しい持ち主のもとでさらに歴史が紡がれていく――ロッピスは、そんな物語を繋ぐ場所でもあるのです。

「消費」から「循環」へ。持続可能な選択の価値
北欧では、「サステナブルな暮らし」は意識的に取り組むものではなく、日常の一部として溶け込んでいます。
人々は家具や衣類、日用品を選ぶ際に、「この先も長く使えるか?」を基準に考えます。ロッピスで人気のヴィンテージ家具は、シンプルで飽きのこないデザイン、耐久性のある素材、職人技が光る作り。こうしたアイテムは、持ち主とともに時を重ね、新たなストーリーを紡いでいきます。
また、ロッピスの魅力は「新しい価値を見つける楽しさ」にもあります。新品にはない、時を経た美しさや、持ち主の暮らしの記憶が刻まれたアイテムとの出会い。その一期一会の喜びが、ロッピスを単なるマーケット以上のものにしているのです。

日本の暮らしにロッピスの精神を取り入れるには?
では、日本の暮らしにロッピスの視点を取り入れるには、どうすればよいのでしょうか?
1. 「身近な人とシェア」する習慣を育てる
まずは、自宅の家具や雑貨を見渡し、「まだ使えるけれど、自分には合わなくなったもの」を探してみましょう。
友人や家族と不用品を交換し合う「ミニ・ロッピス」を開くのもおすすめです。フリーマーケットやシェアリングイベントに参加することで、自分にとって不要なものが、誰かにとっての宝物になることを実感できます。
2. 「長く使えるもの」を選ぶ意識を持つ
新しいものを購入するとき、「この先10年、20年と使えるか?」という視点で選んでみましょう。
北欧の家具や雑貨は、シンプルで飽きのこないデザイン、経年変化を楽しめる素材が多く、長く愛用できるものが豊富です。この視点を取り入れるだけで、物との付き合い方が大きく変わります。
3. 「捨てる」前に「次の使い手」を考える
不要になったものを手放すとき、そのまま捨てるのではなく「次の持ち主」を考えてみましょう。
リサイクルショップを活用する、オンラインのフリーマーケットに出品する、地域のシェアリングイベントに参加する――物を循環させる方法はたくさんあります。
まとめ|ロッピスを日常に取り入れよう
ロッピスは単なるマーケットではなく、「物との向き合い方」を見直すきっかけを与えてくれる場。
何気なく物を手放す前に、その行き先を考えてみる――それだけで、暮らしのあり方が大きく変わるかもしれません。
北欧の人々が大切にしている「持続可能な暮らしの知恵」を、日本の暮らしにも少しずつ取り入れてみませんか?
使い捨ての時代から、「受け継ぐ」暮らしへ。
それが、より豊かで心地よい暮らしへの第一歩になるはずです。